ぼくのおじさん2
yaozoです。
私が大学生の冬、銀座の山下書店で、今は亡き伊丹十三さんと会ったことがあります。
伊丹さんは大学生の頃の私のアイドルの1人でした。
若い方は、伊丹十三さんのことを映画監督としてしか認識していないかと思います。
「ぼくのおじさん」について投稿を書く際に、ついつい伊丹十三さんのことを思い出してしまいます。
なにも、伊丹さんが本当にわたしのおじさんなわけではありません。残念ながら。
伊丹十三さんとぼくのおじさん
なぜ、ぼくのおじさんと伊丹十三さんが繋がるのか。
伊丹十三さんのプロフィールを確認するとわかってもらえるかと思います。
伊丹十三さんは、高名な映画監督伊丹万作の子息として生まれます。
その後、商業デザイナーやイラストレーターとしてキャリアをスタートし、持ち前のルックスを活かして俳優に転向します。
『北京の55日(1963)』『ロード・ジム(1963)』といった海外の映画に出演します。
そして、その際のあれこれを記したエッセイを刊行します。
それが『ヨーロッパ退屈日記(1965)』『女たちよ!()』
その後伊丹さんは、1970年代に入ると、テレビマンユニオン(是枝監督の古巣であるTV制作会社)で、『遠くへ行きたい』というドキュメンタリー番組の制作に携わります。
また、70年代後半には『アフタヌーンショー』に出演し、犯罪事件等を緻密なイラストとともに解説し、レポーターをやっていました。怖い事件をとても面白くレポートしてくれるのです。
私はこれらのTV番組をリアルタイムで見ていましたので、伊丹さんとの遭遇は、「TVに出ているタレントみたいな人」という感じでした。
その後彼は、岸田秀の『ものぐさ精神分析(1977)』と出会い、彼の主張する「唯幻論」に傾倒することになります。
彼との共著、『保育器の中の大人 精神分析講義』と刊行するまでになります。
でここで、彼は岸田氏を中心にして、自身の周囲の学徒やアーティストを総動員した現代思想の雑誌『モノンクル』を刊行するわけです。
キャッチコピーはこんな感じ。
ちょっとこっちへおいでよ
君の心について話そうよ
『mon oncle(モノンクル)』──フランス語で「ぼくのおじさん」という意味です。
1981年、48歳の伊丹十三氏が心理学者であり精神分析家の岸田秀さんとの出会いをきっかけに、自らが責任編集し、当時関心を深めていた精神分析をテーマにさまざまな話題を提供する雑誌を創刊。「ボクのおじさん」という誌名のとおり、親とは違う風通しのよい関係、話し言葉で、同時代の課題を捉えようとする画期的な企画でした。
創刊号には、自身はもちろん、岸田秀さんをはじめ、精神科医の福島章さん、糸井重里さん、南伸坊さん、栗本慎一郎さん、赤瀬川原平さん、タモリさん、YMOの3人、玉村豊男さん、ますむらひろしさん、寺山修司さん、田中小実昌さん、浅井愼平さん、萩尾望都さん、蓮實重彦さん、村松友視さんなど、そうそうたるメンバーが名を連ねています。
ここで紹介されている人々は、私にとって伊丹さんの「お墨付きの立派な人」ということで、この雑誌が私の読書生活の基礎をつくることになるわけです。
ということで、「ぼくのおじさん」というと伊丹十三さんを思い出すわけです。
ついでにプロフィールの続きを書いておきます。
彼はその後も、『吾輩は猫である(1975)』『もう頬杖はつかない(1979)』『細雪(1983)』『家族ゲーム(1983)』などに俳優として出演しています。
そしてついに満を持して、『お葬式(1984)』で映画監督としてデビューし、大ヒットメーカーとなるわけです。
『マルタイの女(1997)』まで、10本の作品を残しています。
とにかく、あんな人が自分のおじさんだったらさぞかしうれしいだろうなぁ、と思うわけです。
おじさんの役割
内田樹先生が、レヴィ=ストロースの親族論を語る論考の中で、「タイプの違う二人のロールモデルがいないと人間は成熟できない」と言っています。
この二人の同棲の成人は「違うことを」言う。
この二つの命題のあいだで葛藤することが成熟の必須条件なのである。
成熟というのは簡単に言えば、「自分がその問題の解き方を習っていない問題を解く能力」を身に付けるということである。
父と伯叔父は「私」に対してまったく違う態度で接し、まったく違う評価を与え、まったく違う生き方をリコメンドする。
この矛盾を止揚するフレームワークはひとつしかない。
それは、「この二人の成人のふるまいはいずれも『私を成熟させる』という目的においてはじめて無矛盾的である」という回答に出会うことである。
だが、この父と伯叔父を統合するフレームワークは父も伯叔父もどちらも与えてくれない。
子どもはこれを自力で発見しなければならない。
この後内田先生は、近代の核家族からは「伯叔父」が排除され、「私」が成熟する機会が奪われていく悲劇を嘆くわけです。
とまぁ、長く引用させてもらったのは、他でもない、まさに内田先生がこの親族論で語っている典型的なことが、私と父とおじさんとの間でおこっていた、ということが言いたかったからです。
だからといって、私が「社会的成熟」を果たせたか、「包括的フレームワーク」を手にできたかは、残念ながらまた別問題なのですが、少なくとも私はその幸運な機会が与えられていた最後の方の世代であることは間違いないのではないかと思います。
本当の「ぼくのおじさん」
父と、意見や人生観(のようなものはなかなか直接的に耳にしませんでしたが)をことにする伯叔父はたくさんいましたが、このおじさんがその最たるものだったわけです。極北といっていいでしょう。
なのに、盆暮れには、実姉目当てに我が家にやってきて、義兄に小言を言われる、というのを繰り返していました。
これくらい水と油の関係は10組もいる、「父+おじさん」のカップリングの中で、最強のものでした。
そもそも父の母、つまり私の父方の祖母は、私の母が我が家に嫁いでくることにあまり乗り気ではなかったようです。
いわく、●●家(母の実家)の人間と我が家では、家風が違いすぎる、といって祖母はその結婚に随分気をもんだらしいです。唯一東京に出て嫁いだ父方のおば(父の姉)からそのあたりのことをよくききました。
そのおばさん自身もかわいい末っ子の実弟と私の母との結婚に関してはもろ手を挙げて賛成と言うわけではなかったような気がします。はっきり言われたことはありませんが、言葉の端々でそういったことが感じられました。
そのおばさんは「蛇が出るからこんな田舎は嫌だ」といって生家を飛び出して、中学を出てすぐに人伝手に上京し、銭湯で下働きをしてはげみ、その後同郷出身の男性と結婚しました。
私の上京直後、その家に居候していたので、よく知っていますが、始終夫婦ケンカばかりしていたようなので、それほど夫婦仲が良かったとも思えませでした。
でもそのおばさんと私とは10人いるおばさんの中でも最も馬が合いました。
なにやら彼女は、私の中に、大好きな実弟の面影を見ているような気がしましたが、私もそのおばさんの進取の気性(上京して腰を落ち着けた唯一の親族ですし)やべらんめぇで直截な感じが大好きでしたので、実の母より気が合ったと言っていいかもしれません。
「ぼくのおばさん」の話になってしまいましたが、ぼくのおじさんに1つの転機が訪れます。
東京暮らしをしていたおじさんが、盆暮れに帰省し、ぼくら甥っ子をからかう、というパターンがそこそこ定着しだしたころ、どんな理由があったのか知りませんが、おじさんは東京暮らしをやめて、私の地元の県庁所在地である地方都市にUターンしてくることになりました。
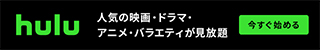






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません