ぼくのおじさん1
yaozoです。
元号が令和に変わり、数か月が経ち、新元号にもやっとなれてきました。
私は昭和生まれです。
なので現時点で、昭和、平成、令和と少なくとも3つの時代を生きているわけです。
だからまさしく、私が生まれた昭和については、「昭和は遠くなりにけり」といった感慨がわくわけです。中村草田男は名前がかっこいいのに加えて、いいこと言いますね。すごい。
元号が変わる直前あたりにやっと気づいたのですが、私は昭和生まれではありますが、生きている年月は実は平成の方が長いのです。
平成が31年までですから、話を単純にすれば62歳ぐらいより上でない限り、そのようなことなります。私は50代後半ですから当然、平成をより長く生きたのです。
しかしなんとなく、自分が平成の人間だ、なんていう気分がしたことがありませんでした。
おそらく昭和生まれで、物心ついて社会人になったときにまだ昭和だったから、ということからだとは思います。
平成になる瞬間のことも覚えてますし、新元号に対してみなが口々にいっていた「なんか違和感あるなぁ」という言葉も共感がわきます。
そして、結局その違和感は、平成が終わるまで続いたような気がします。
令和は二回目の改元体験だからなのか、なんとなくすんなり受け止められているように思えます。
今私は令和の人間なような気がして生きています。
一番若いおじさん
私は1960年代初頭に、片田舎で生まれました。
同じような生まれの人によくあることだと思いますが、私にはおじさんとおばさんがたくさんいます。
まず、私の父には上に3人の姉がいます。
そして、私の母には7人の兄弟がいます。
その全員が、少なくて2人、多い家で7人くらいの子宝に恵まれています。
とにかく、私には叔父さんと叔父さんあわせて10人のおじさんがいることになります。
それだけいれば、おじさんにまつわる話は書き出すときりがありません。
元号が改まって一段落したこのあたりで、昭和に思いをはせて、私が最も影響を受け、私の中の昭和を強く感じさせてくれる、一人のおじさんの話を書きます。
おそらく、1960年代後半~1970年代中盤にかけての日本の地方における、親戚の中に必ず一人はいる「悪いおじさん」と「ナイーブな甥っ子」という関係の、1つの類型が抽出・記録できるのではないかと思います。
そのおじさんは、私の母方の一番年下の叔父にあたる人で、母は9人兄弟の上から4番目なので、母とそのおじさんとはそこそこ年が離れています。私にとって、一番年の近い「若いおじさん」になるわけです。
気分としては、「とても若いおじさん」と「とても年の離れたお兄さん」の間位の存在でした。
母が小学生・中学生時代のころには、8人の中で女が1人ということもあり、母がそのおじさんをおぶったり、連れて遊んだりと、随分かわいがったようです。
おじさんは長じて東京に出ました。
何をして生活していたのかは知りません。
唯一わかっているのは、東京にいるころに、ボクシングジムに通っていたことくらいです。
ボクシングといえば、家に白黒テレビがやってきた1960年代中盤に、キックボクシングと共に、少年たちをとても楽しませてくれたエンターテインメントでした。
キックボクシングで言えば沢村忠の「真空飛び膝蹴り」という必殺技が人気でした。「キックの鬼(1970-1971)」というアニメにもなり大人気でしたね。毎週欠かさず見ていました。
ボクシングでも輪島功一やガッツ石松などの日本人世界チャンピオンが続出して大活躍し、ゴールデンタイムで生中継をしていました。固唾をのんでテレビにくぎ付けになっていた男子は少なくなかったはずです。
ですからその当時、ボクサーというのは、かっこいい存在でした。上の日本人チャンピオンも活躍していましたし、折しもブルース・リー映画の流行とシンクロしていますので、世は第何次だかの格闘技ブームでした。
リーにならって、私たちはみんな、里山に入っては、自分で適当な木や竹を切って、いくつものヌンチャクを作って振り回しました。本当に何本も作りました。プラスティックの水道管を切って作ったりもしました。ある種の競争のように、男子学生はみなヌンチャクを作っていたのです。振り回しては、頭にぶつけ、ぶつけては振り回し、といったことを、あきるまでやっていました。
私は考えが幼かったのもあり、中学生になっても、ブルース・リー関連の書籍や写真集を買っては、「いいなぁ」「かっこいいなぁ」などと、映画館で見てきたリーの姿を思い出していたのです。
今のように、見たいときにすぐにストリーミングプロバイダーやYouTubeで、映画でもなんでも見れるような状況ではありませんでしたので、スチール写真を見ながら、頭の中でそれをムービーにおこしてみていたわけです。
寝る前の物語と入浴中の音楽
ムービーにおこすと言えば、話は少し脱線しますが、私の小さいころの夢は、夜寝るときに、なにか映画かTV番組をみながら眠れるといいなぁ、というものでした。
少しでも、それに近いことをしようと、就寝する前に簡単な切り絵を何種類か作っておいて、懐中電灯をあてて天井に色々な絵を映し出して楽しんでました。ほんの5-6分くらいだと思いますが、とてもうっとりする時間だったことを覚えています。
また、中学生になりポップスに夢中になり、お風呂に入るときに音楽を聴きたいと思い立ち、父に頼んで、スピーカーを作ってもらいました。
父は手先が器用なので、スピーカーのコーン部分を車の廃材だか古いラジオから取り出してきて、スピーカーボックスを手作りし、見事なモノラルスピーカーを作ってくれました。上下左右には、壁紙の残りなのか、化粧布まで貼ってある凝りようです。とてもうれしかったことを覚えています。
そのスピーカーを、愛用のラジカセにつなぎ、中学生・高校生の頃は、お風呂に入るときに、お風呂の入り口のすぐ前に置いて、ビートルズやらなにやら、大好きなポップミュージックを鳴らしながらお風呂に入っていました。
結構大きな音で鳴らさないとよく聞こえないので、ボリュームを上げてましたが、なぜかそれで起こられた記憶がありません。
今思うと、家ではあまり笑わず、わりに厳しいイメージだった父が、よくこんな手間をかけてくれたなぁ、と思いますが、その時は単にうれしくてガンガン愛用していました。
自分が親になってわかりますが、おそらく父も、自分の作ったスピーカーを息子が毎日毎日使って喜んでいるのですから、相応にうれしかったはずです。
だから、母が何か小言を言ったとしてもスピーカーの製造者として「まぁ、喜んでるんだから、やらしておけ」って感じだったんでしょう。
で、40年数年の時を経て、今では私は、就寝時には必ずタブレットを寝室に持ち込み、映画やドラマを見ながら眠りに落ちますし、お風呂に入るときには、防水式Bluetoothスピーカーを持ち込んで、スマホの音楽を飛ばして聴きながら入浴しているわけです。
「三つ子の魂百まで」ということで40年経っても同じようなことをやっているわけですね。
それはともかく、おじさんのボクシングジムの話に戻ります。
ボクシングと催眠術
なにしろ片田舎の村のことですから、ボクシングを東京のジムで習ってたなんていうのは、相当すごいことでした。
小さいころから母の兄弟の中では一番やんちゃで、祖母や母の手を焼かせていたと聞いていたおじさんですが、そういった常識的な評価と同時に、田舎にはない都会の空気を持ってきてくれる唯一の存在でもあったのです。
そのおじさんは、盆暮れの里帰りのときは、必ずと言っていいほど、おじさんの実家(彼の父母や長兄の住む家です。
同じ村の、我が家からほんの数百メートル離れたところにあります)よりも先に、まずは実の姉の嫁ぎ先である私の家にあがりこんでは、姉に甘え、私たち兄弟(一つ上の兄と私)をからかう、というのが決まり事になっていたのです。
そして、ある年のお盆に、またぞろ実姉に甘えようと、私の家に立ち寄っていたときのことです。
ひとしきり東京の自慢話をして気が済んだおじさんは、やおら手にしたボストンバッグから、白い包帯のようなものを取り出し、これがボクシンググローブを付ける前に巻く「バンデージ」だと教えてくれたのです。
ボクシングの試合が終わった際に、勝者はグローブをはずしますが、その手には白いバンデージが巻かれています。
それくらいのことはわかっていましたので、素直に「こりゃ、すごい」と感動したわけです。
おじさんは、私の小さな手にバンデージを巻き付けてはほどき、巻き付けてはほどき、と文字通り手取り足取りで、バンデージの巻き方を何度か教えてみせます。
でも、小学生の私には、複雑すぎて覚えられません。長じて、私自身がキックボクシングを習うことになったときに覚えることとなりましたが、これは小学生が2-3回やって覚えられるものでもありません。後に、無茶ゆってたことがわかりました。
おじさんは、「つまらんやつだなぁ、これくらい覚えられなくてどうする」などと、笑いながら上機嫌でバンデージを取り上げました。
「それじゃ、プロレスしよう」と言い出し、我々兄弟とおじさんという、どう戦うかわからいようなプロレスごっこがはじまります。
誰が誰を攻撃しているかわからないうちに、私がおじさんから「電気あんま」などの技をくらって、「やめてぇ」と半泣きになりながら終わる、という感じのばかばかしいお遊びがちょくちょく行われました。
長ずるにつれ、兄はませた小さな大人のようになっていきましたので、いきおいおじさんのターゲットは私に集中する度合いが増していきます。兄はお小遣いをもらったら、そこそこ話に付き合った後、うまいこといって自室に戻ります。
そんな頃の別の帰省の回に、「おじさんが、東京で催眠術を覚えてきたから、今日は特別、おまえにかけてやろう」といい、私1人が実験台にされることになりました。5円玉にひもを通したなものを目の前でブラブラさせながら、「おまえはだんだん眠くな~る」などと定型的なフレーズをそれらしくのたまうわけです。
もちろん眠くなろうはずもなく、目をパチパチしていると、「眠くな~る~!」などと目で脅してきて、無理やり、目を閉じさせようとします。
いくら小学生とはいえ、あまりにばからしいので、ぼけ~っと座っていると、「な~んだ、つまらん。お前にはかからんようだ。催眠術は素直な奴にしかかからんからな!とかくおまえら兄弟は真面目過ぎていかん。」などと捨て台詞を吐いて、向こうに行ってしまいます。
私はほっと安心します。よかった。
父 vs おじさん
さて、おじさんの独壇場の時間も数時間すぎ、父が仕事から帰宅します。
おじさんは挨拶します。義理の兄ですから、お愛想の一つもいいながら、人懐っこい顔でご機嫌を伺います。
それを無視するかのように父が言います。「前に止めてある車、おまえのか。随分車高が低いんだな。あんなんで車検通るのか。つかまらんのか。」などと早速説教がはじまります。
なにしろ父は、村の路線バスの運転手第一号でしたので、安全運転や交通法規順守に関してはかなり厳しいところがありました。
1960年代の片田舎のことですから、今でいう国内線のパイロットみたいな気概を持ってやっていたのではないだろうかと想像します。
「大丈夫なんですよぉ。あれくらいは~」などと、どう見てもバレバレの嘘を返します。つまり、そのころすでに20歳もこえていたおじさんは、いい年して「シャコタン」の車に乗っているヤンキー崩れのカッコ悪い大人だったわけです。
嘘と分かっている堅物の父は、「こいつ、また来やがって」といった不機嫌を隠そうともせず、いつものように手酌で晩酌をはじめます。
父が帰ってきたところで形勢が悪くなったと見たおじさんは、仕方なく、「よ~し、尊敬するお兄様のお顔も見れたことだし、大好きな姉ちゃんは元気そうだし。
しょうがないから、ババぁのところでも顔出しますかね~」などと大声で宣言し、実家に行くと言って我が家を後にします。
我々兄弟が小学生だったころの盆暮れは大体そんな感じで進んでいきました。
あんなおじさんでしたが、そこは昔のこと、毎年盆暮れにはちゃんと帰省していたように記憶しています。
まぁ少なくとも我々兄弟がまだ小学生の頃は。
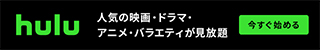

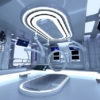





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません